「事業計画書」で事業の全体像を説明しよう
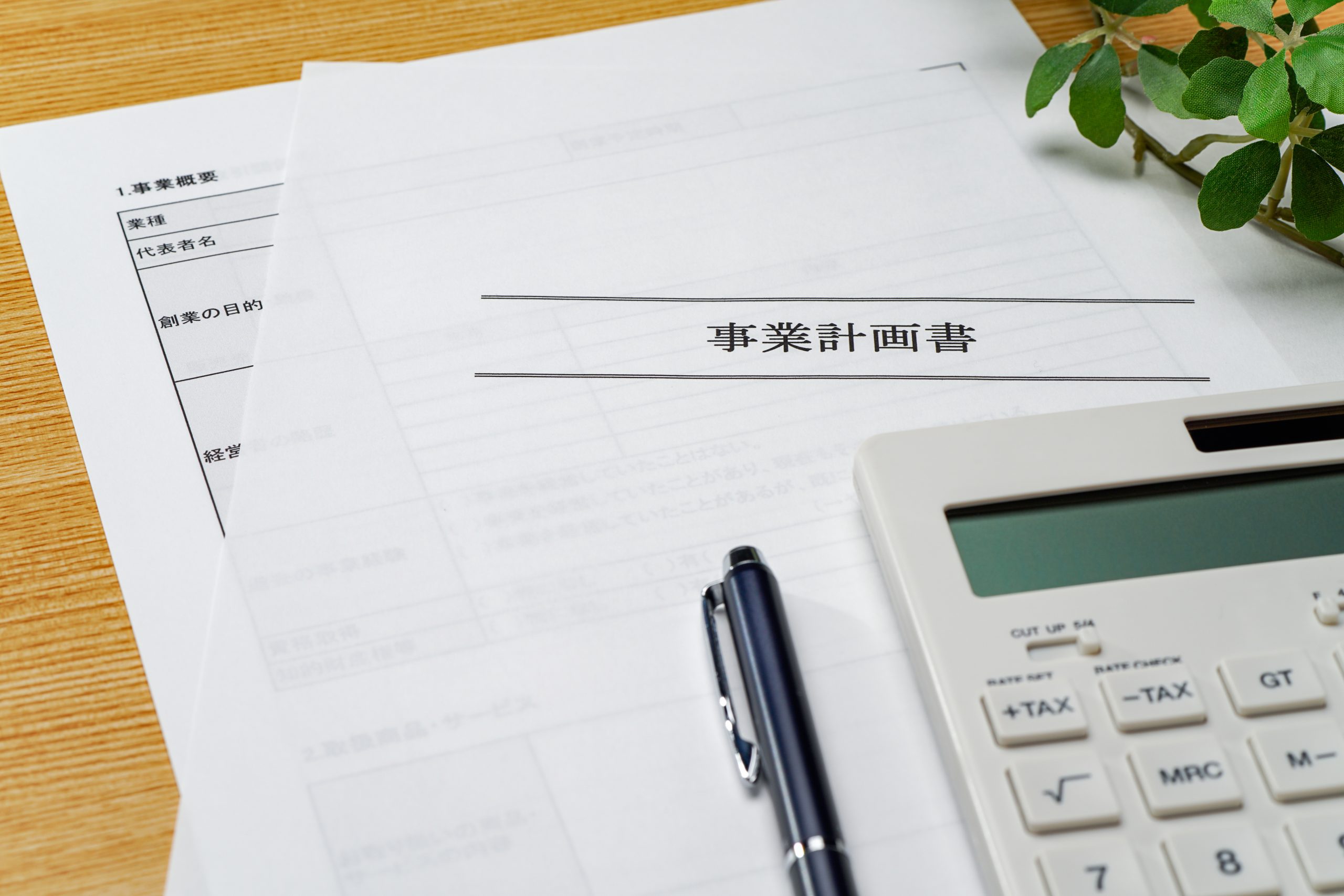
この「わくわく補助金」に応募し、かつ、採択されるためのカギとなるのが「事業計画書」です。起業家が「自分はどんな事業を始めようとしているのか」「始めた後、どう事業を発展させていくのか」等について、いろんな側面から説明するものです。
読む人(審査員)が事業の全体像を理解し、「こんな事業が和歌山にあったらいいね」「この事業ならきっと和歌山を活性化してくれそう」「補助金後も、自律的に成長していきそうな事業だ」と思ってくれたら「採択」される…といっても過言ではないくらい重要な書類です。
「事業計画書」にはどんなことを書けばいい?
では、事業計画書には具体的にどんな内容を記載するのでしょうか?
補助金に応募するだけでなく、起業する前にじっくり自分の事業の内容を検討する機会としても活用できます。(事業計画書の様式は、からダウンロードできます。)
主な項目は次のとおりで、空欄の状態でも9ページと書きごたえのある様式です。
- 応募者の概要等(お名前、住所、生年月日…等)
- 申請概要(事業テーマ名、概要、起業のきっかけ…等)
- 事業の社会性・必要性(顧客と市場の状況、商品・サービスの概要、地域課題・ニーズと解決策、競合状況と優位性…等)
- 事業の継続性・事業性(中期収支計画と算定根拠、スケジュール、デジタル活用、資金計画…等)
伝わる「事業計画書」を書くための3つのポイント
大事なのは、事業計画書をどう書けば、読む人(審査員)に「いいね」と思ってもらえるかです。そこで、以下の3つのポイントをお伝えします。
1.審査項目・基準をバッチリ押さえる
審査の際は、審査項目・基準に沿って点が入ります。つらつらとマスを埋めていても、審査項目・基準に関係のないことばかりであれば、一向に点が入りません。審査項目は公募要領に記載されていますので、必ず確認してください。
2.問われたことにビシッと応える
質問内容に応えることが大事です(ピント外れと思われないように…)。その上で読む人が「きっとこの事業は成功する」と想像できる説得力のある証拠・根拠を(できれば数字と共に)提示できると強いです。
また、思いつきではなく、しっかりと考えが練られている、工夫されているということが伝わることも大事で、「短期的vs長期的」「現在vs将来」「地元vs全国(全世界)」等の視点でも考察したことがわかるようにしましょう。
3.今流行の生成AIを活用して作成する(ことも可能です。)
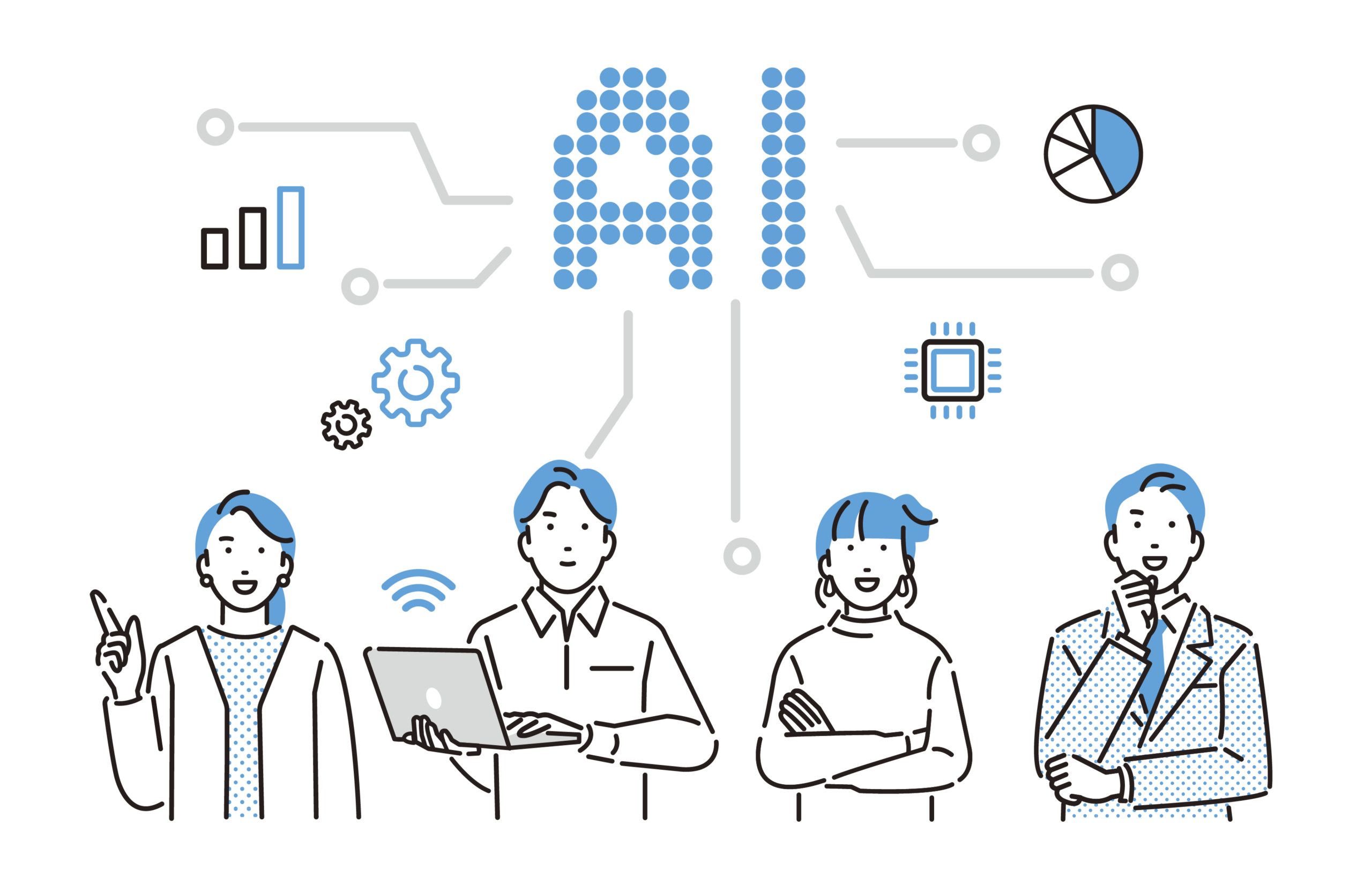
「アイデア出し」「情報収集」「文章作成」を優秀なアシスタント(AI)と対話しながら、苦手な部分をサポートしてもらいましょう。
AIを賢いアシスタントに育てるコツには、「背景」(わかやま地域課題解決型起業支援とは何か?)、「審査基準」「自分はどんな事業をしようとしているのか?」などの情報を提供することです。難しければ、AIに「作成するのに、私のどんな情報が必要ですか?」と尋ねてみてもいいかもしれません。
とはいえ、生成AIは一般的な回答になりがちですので、独自性のある事業に仕立て上げるには、起業家自身の思いを文字に託すため、最後の確認・修正は必須です。
一例として、「ChatGPT」との対話のリンクを貼りますので、ご参考にしていただけましたら幸いです。
誰かに相談したいと思ったら
それでも作成に困ったという方は、下記のイベントや相談会にぜひご参加ください。
これらのイベント以外にも、チームわくわくでは随時ご相談をお受けしておりますので、こちらのよりお申し込みください。
みなさまからのお問い合わせ・ご相談をお待ちしております。
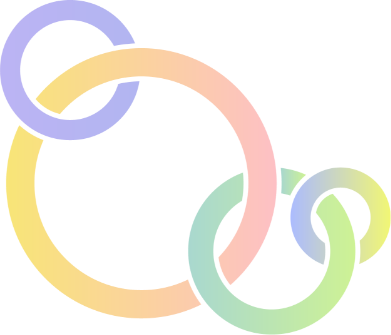
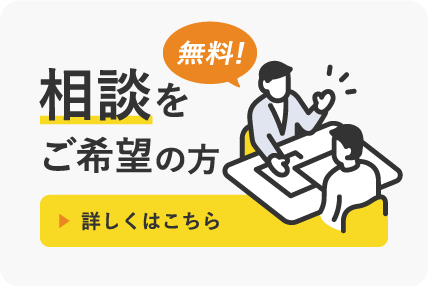
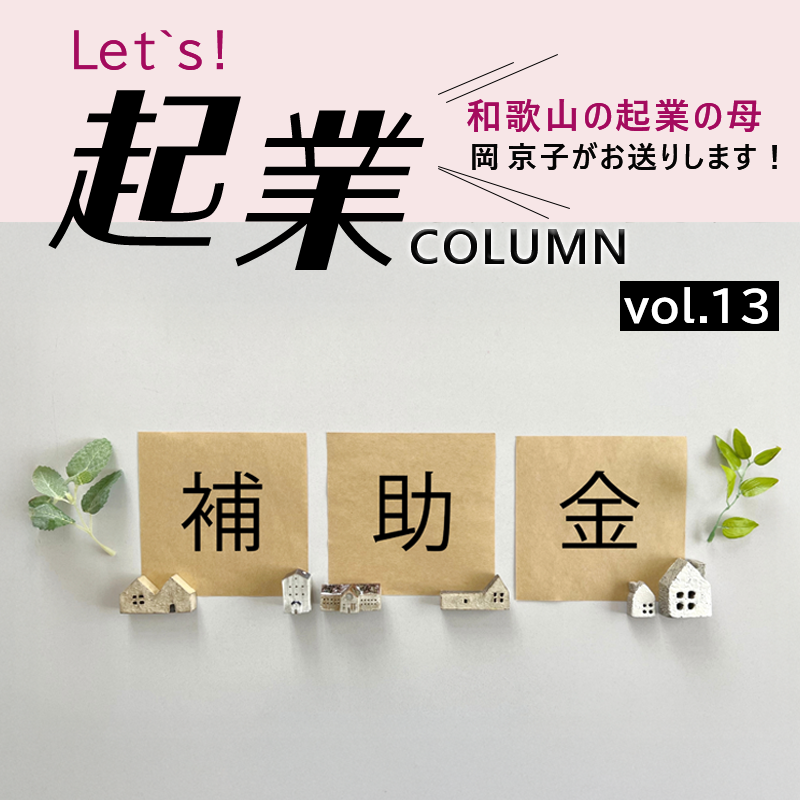




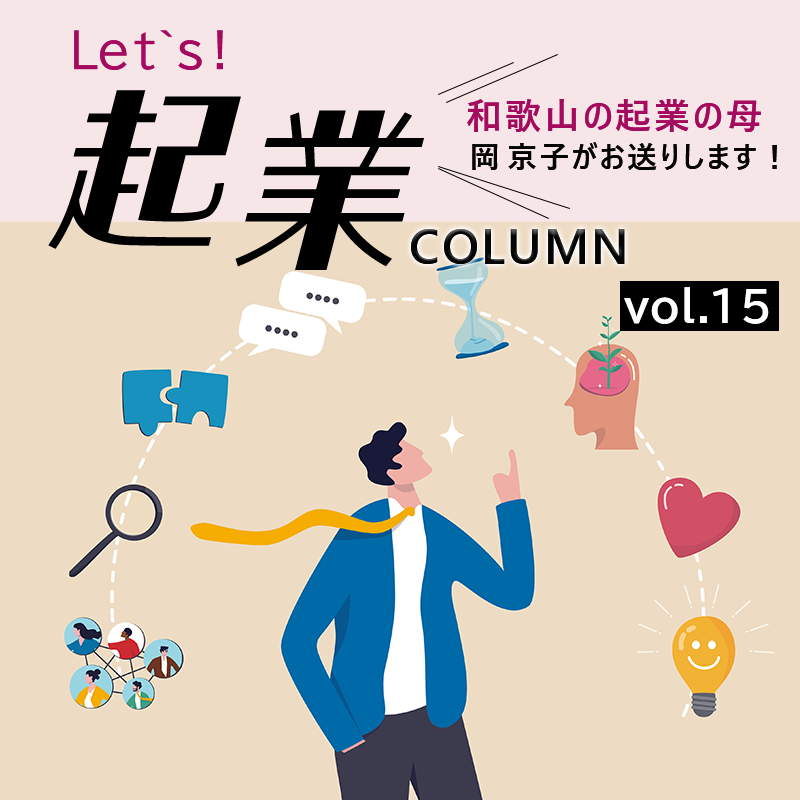


中小企業診断士。大卒後、東京・ロンドンで編集者として活動後、メガバンクにて為替取引に従事。帰国後に㈱きのくに未来ビジネスセンターを承継し、県内初の創業スクール(中企庁事業)を受託する等、創業や中小企業経営の支援継続中。