たくさんある共同利用可能な研究機器
本当はひとつひとつの機器についてどんな機器なのか、何ができるのか紹介したいのですが、たくさんあってキリがないので下のリンクから一覧のページを見てください。簡単にですが説明があります。
最新導入の研究機器のご紹介
最近導入され、ぜひご紹介したい機器がありますので取り上げたいと思います。
蛍光・明視野・位相差など、1台で様々な観察方法に対応した蛍光顕微鏡です。観察・撮影・解析の操作が簡単で複数の画像を一括解析することができます。タイムラプス撮影機能により培養条件下の細胞の長期観察なども可能です。

B005 オールインワン蛍光顕微鏡
物質(主に有機化合物)の分子構造を原子レベルで解析するための装置です。通常の溶液サンプルだけでなく、固体サンプルの高分解能測定にも対応しています。

A025 核磁気共鳴装置
室温から-170℃の温度範囲で結晶構造を解析することができます。2種類の強力な線源が用意されているので、どのような組成でも、小さな結晶でも測定することができます。

A027 単結晶X線構造解析システム
測定対象の微量な試料を高温で燃焼分解して、試料中に含まれる水素、炭素、窒素をそれぞれ定量的に
H2O、CO2、N2に変換して各成分を検出して定量することで、有機化合物を構成する元素の組成(H、C、N)を決定する装置です。

A007 有機微量元素分析装置
どうやって利用するのか
研究機器それぞれに利用料金の時間単価が決まっていて、利用する時間によって利用料金が積算されます。また機器によっては消耗品料などがかかる場合もあります。まずは利用申請書に必要事項を記入して、窓口まで提出してください。あとは窓口の担当者が機器の管理者などと連絡をとり、利用希望日を調整します。利用日当日は管理者から機器の使用に関する指導を受けてご利用いただきます。
利用申請書とその提出先
提出先 和歌山大学 研究社会連携課 研究機器共同利用担当
jointuse[at]ml.wakayama-u.ac.jp ([at]を@置き換えてください)
お問い合わせ先
いくつかの注意事項
研究機器の利用効率を上げるためのこの取り組みですが、いくつかの制限があります。
まず、本来は本学の研究教育目的で導入された機器ですので、利用は本学の研究目的利用が優先されます。また以下の理由によって利用をお断りする場合があります。
- 機器が故障などによって使用できない場合
- 管理者が多忙で対応が困難な場合(利用時期をずらしていただく場合もあります)
- 持ち込まれる対象物が使用に適さないもしくは機器の損壊が予想される場合
ご理解を頂ければと思います。
利用時間が長時間になる場合、対象物が多数の場合など詳細についてはご相談いただければ、それぞれに応じた対応を検討します。お気軽にご相談ください。
今回は本学が所有する研究機器が学外の方々にもご使用いただける制度についてご紹介しました。次回は産学連携イノベーションセンターURA室のスタッフをご紹介したいと思います。
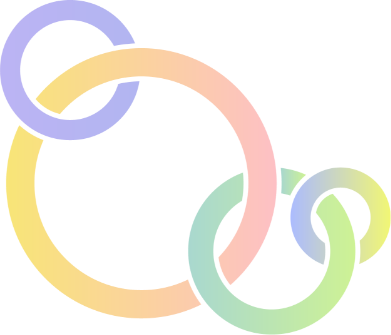
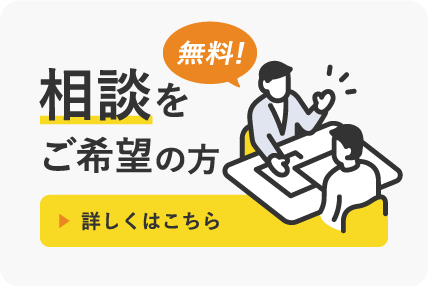










和歌山県内唯一の国立大学法人和歌山大学の中に設置された、主に学内研究者の研究情報の発信と外部資金獲得を業務とする組織です。最新のお知らせなどは産学連携イノベーションセンターのWebページをご覧ください。https://www.wakayama-u.ac.jp/cijr/